- 『これは何て言うんだろう』と常に意識する
もちろん、英語学になると難しかったり、高尚になったりしますが、たいていの人の目標は「話せるようになりたい」のではないでしょうか。日本語で話せるようになったことを、英語では何と言うのか、それを把握して、言う練習をすればいいだけのことなんです。難しい理論や高尚な学問ではないということです。
『これは何て言うんだろう』という疑問と好奇心が、吸収力につながります。
- 言葉はリズムだ、音楽だ
言語スキルには、「話す・聞く・読む・書く」の四つの基本スキルがあります。これら4つのスキルをバランスよく
そなえることが肝要です。このなかでも、まず「話す・聞く」が基本。つまり音の認識なくして外国語はマスターできません。
しかし、日本人は英語を「読む」と「書く」の2つに偏って学んでいる傾向があります。
だから音を何より優先させる。
訳すよりも音読を心がける。
カラオケで歌を歌えるようになるのと同じやり方で「聞く」と「話す」の部分を補っていくのです。
| 基本的な「音」の認識とは |
カタカナは英語の発音を表していない。 |
| 日本語も子音と母音の組み合わせである。 |
| 英語と日本語とでは、子音も母音も異なる。 |
| 発音するときに使う頬や舌の筋肉が異なる。 |
| 発音の練習は、リスニング力の強化につながる。 |
もう少し詳しく解説してみましょう。
| カタカナは英語の発音を表していない。 |
外国語を、最も近い音のカタカナで表記するという方法は、とても画期的な方法です。
でもそれは、日本語にない外国語の発想や物、概念を表すのに素晴らしい方法というだけで、発音を理解するためのものではないはず。
カタカナで一所懸命話しても相手に通じなかったり、とんでもない誤解を生じるのは、当然でしょう。だって、カタカナはあくまでも「日本語」なんですから。 |
| 日本語も子音と母音の組み合わせである。 |
何気なく話している日本語の、一つ一つの音をどう発音しているか分析してみてください。
口はどんな風に開けているか、舌はどのように動かし、どこに着けたり離したりしているかです。
そして、日本語の一つ一つの音も、ローマ字で書いたときのように、子音と母音の組み合わせなんだということを認識しましょう。
面白い実験があります。オープンリールのテープデッキやmidiの編集ソフトを持っている人はやってみてください。
「もしもし」を逆回しにすると、どう聞こえるでしょう。
正解は「しもしも」ではありません。「いしょみしょん」のように聞こえます。
これはローマ字で書くとよく判ります。"MOSHIMOSHI"を逆に書くと
"IHSOMIHSOM"ですね。
これが「いしょみしょん」のように聞こえるわけですが、これは、何気なく一つの音だと思って発音していても、実はちゃんと子音と母音を組み合わせて発音している証拠なんです。
第2条のトップへ戻る |
| 英語と日本語とでは、子音も母音も異なる。 |
日本語の音はいくつありますか。<アカサタナハマヤラワガザダバパ×あいうえお>で75、ギャギュギョやピャピュピョなどを入れても、87。多く見積もっても90ありませんね。
英語はどうでしょう。子音字BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ(半母音と言われるwyも)×母音字aeiou(それぞれ発音は2つ以上)少なく見積もっても210です。
さらに、子音が2つ3つ連続することもあります。
カタカナではとうてい表しきれないということがおわかりでしょう。 |
| 発音するときに使う頬や舌の筋肉が異なる。 |
近いと思っている音でも、頬や舌の筋肉の使い方・緊張のさせ方は違うのです。
本来、発音は、よく聞いて、同じ音を出しているか、自分の音と比較して修正する、という方法で修得するものです。しかし、ある程度母国語に慣れた年齢になると、同じ音を真似たり、自分の耳を頼りに修正することが難しくなります。顔の筋肉も、柔軟性を失っていきますから、外国語の発音は小さい頃に身につけた方がいいと言われるわけです。
でもあきらめることはありません。カラオケで何度も歌って覚えてしまうように、何度も聞いて、口と耳に覚えさせればいいのです。 |
| 発音の練習は、リスニング力の強化につながる。 |
特に日本語にない子音はたいへんですよね。
LとR、SとSH、BとV、FとH、MとNとNG。
Lは舌の奥を前に延ばすように緊張させて、喉をあけた「あ」、Rは舌の奥を喉の方に引き寄せて、口をあまり開かずに喉でうなる「う」だと思った方がいいくらいです。
Sの音は日本語では「さすせそ」の子音ですね。それが日本人の方には特に難しいようですが、とりわけ「し」を連想させてしまう綴りの場合は問題です。
sea, seat, sit, cityなどなど、「し」の音ではまるで意味が異なります。同じサ行に書かれていますが、「し」は発音から言えば「しゃ行」の「しゃししゅしぇしょ」です。
Sの音は、上下の前歯をぴったりとかみ合わせて、歯の隙間から澄んだ息を滑り出させましょう。
Vは上の歯で下唇を噛むなんて、そんなことはたいへんでしょう。むしろ、BやPのように上と下の唇が触らないように、上の唇を上にめくって除け、その上の唇の代わりに上の歯を下唇にそっと当てるようにしないと、スムーズに発音できないでしょう。Fの口も同じです。
さて、日本語の問題です。「さんま」の「ん」と「みんな」の「ん」、「げんかん」の「ん」の発音は同じですか?本当は違うはずなんですが。そして、それが、MとNとNGなんです。
しっかりと発音する練習をして、一つの音から単語へ、単語から文節へ、文節から文へと、スムーズに正しく言えるようにしていくと、リスニングの力にもなっていきます。それは、自分の耳が自分の発する音を基準にして、正しい英語の発音を認識できるようになると同時に、脳が、ある程度の長さの文を音で認識して、貯めておくことができるようになるからなんです。
がんばってみてください。 |
ページトップへ戻る
- 頭の中に情景を描く
―イマジネーションを活用する―
頭の中に情景が描けなければ訳しても意味がない。
どんな人たちがどんな場所で、どんな気持ちを伝えているのか、その裏付けのない言葉なんて、記号の羅列にすぎません。
たとえ日本語訳にできても、その場面が想像できていなければ、その意味が本当に判ったことになるでしょうか。
ノートにはなんでも書く。消しゴムは使わない。
間違ったという事実を残すことの方が、美しいノートを残すより大事。
学習する際には、覚えるべきことだけでなく、注意事項や、間違いなども記録しておくのです。しばらく経って、本当に必要になった時に、新しいテキストを買うよりも、自分で作ったノートの方が、何倍も力になるのです。
ページトップへ戻る
照れていては一生話せない。
日本人は概して照れ屋さんですね。でもそれはDNAに染み込んでいるのですから、いまさら書き換えは、・・・ちょっとね。
だから、 役者になれ。
場面・気持ち・言葉 文法は後からついてくる
「こんな時はこう言う」がわかったら、まず唱える。
そうやって、場面と気持ちに合った言葉が、自然と口を衝いて出てくるようにしていけばいいのです。
その積み重ねなんです、言葉なんて。
文法を考えながら訳していたら嫌になる。
そんなふうに日本語を話している人がいたら、きっと聞いている人は苛々するでしょうね。多少言葉が足りなくても、気持ちって通じるものだ、くらいの気楽さも必要でしょう。
「よし言えた、言えるジャン、自分ってちょっとスゴイ」の積み重ねが大事
ページトップへ戻る
聞き取れてよかった、意味が判った、 を繰り返せ
これが言葉が使えることの喜びであるはず。
これを繰り返して、積み重ねていくのです。
苦痛は積み重ねても、やっぱり苦痛でしょう。
- 辞書は覚えようとしないで、繰り返し引く
引けば引くほど速くなる。引けば引くほど単語は覚える。
読み切ることで、本当の意味が見えてくる。
覚えようとしないで、繰り返し引く。
辞書なくして言語の修得はありうるでしょうか。ありえます。でも、程度によります。
正しく辞書を使わないで、効果的な言語の修得はありうるでしょうか。まず無理でしょう。
さて、英語の学習に必要な英和辞書の正しい使い方を考えてみましょう。
それにはまず、辞書とはどのようなものかを認識する必要があります。
| 英和辞書とは |
英語の単語を、使われている表現の頻度にあわせて、最も近い日本語表現を並べたものである。 |
|
その英単語は、使われている文例から判断された品詞の分類がなされている。 |
| 発音記号が書かれている。 |
| その英単語の使われている例文が挙げられている。 |
| その英単語の語源が表示されている。 |
ざっとこんなものを英和辞書といいます。この条件に当てはまらないものを辞書と呼んではいけません。
ところで、皆さんはどのように辞書を使っていますか。
私が見てきた日本人の大半は、単語の意味を辞書から選んで、訳文の中に押し込めるという手法を取っていました。
これでは、その単語の意味は永遠にわからないのです。
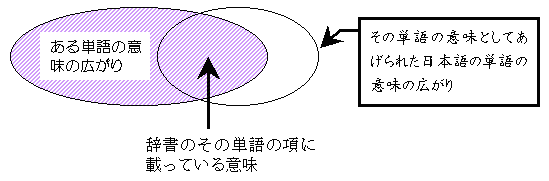
この図は、ある単語が本来持っている意味の広がりと、辞書の限界、辞書に挙げられた訳語から選んでしまう危険性を表しています。
では、どうするか。
辞書は読むもの
辞書は、読んでください。その単語のところに書かれたことを全部読んで、おぼろげにでも、その単語の意味の広がりを感じ取ってください。
「訳す時はめんどくさいし、それでは時間がかかりすぎる」という人は、きっと大勢いらっしゃるでしょう。
そのめんどくささを乗り越えて、時間をかけなければ、ほんとうの英語力は身につきません。
さらにこの図はもうひとつ、重要なことを表しています。それは、
英語と日本語は1対1の直訳対応をしない! ということです。
ものの見方も考え方も違う言語体系です。1対1の対応なんて、偶然の一致以外にはほとんどありません。
文脈の大きな流れの中で、その部分がどのようなことを表現しているのかということを把握して(これを「解釈する」と言います)、それと同じことを日本語で言ったらどうなるか、という作業を翻訳といいます。
それと、発音記号はきちんと読めるようにしましょう。
第8条のトップへ戻る
ページトップへ戻る
- 復習第一
ノートは学ぶ者の唯一の財産
ここでいうノートとは、学ぶ記録ということです。これを残していくことが、自分にとっても、少しずつ積み重なっていく達成感のようなものになるのではないでしょうか。
整理することが復習と心得る。
スラスラと読み返せるまでひたすら読む。
特に、資格試験などを目標にしている方は、これが一番効果があるのです。
さて、英語を身につけたいと思っていても、なかなか思い通りにいかないのはどうしてでしょう。
根気がないから。どこから手をつけたらいいか、わからないから。やってもやっても、底知れぬ沼に足を踏み入れたようで、ちっとも力が伸びた気がしないから。
日本人の学習者の大半の問題は、「目的意識(ゴール)を持っていない」「ゴールが見えない」ということに尽きるのではないかと思うのですが、どうでしょう。
英語をどの程度まで身につけて、それを使って何をしたいのか、どんな人とどの程度のコミュニケーションをとりたいのか、そうしたはっきりした目的意識をもってほしいと、私は思います。
|
あなたが英語を使って何をしたいか、それが目標です。それによってどこから始めるかも、勉強の仕方も、決まってくるのです。 |
六本木で軟派したい。それも立派な目標です。 |
| 海外旅行で英語で買物がしたい。いいでしょう。 |
| 一人で海外旅行を楽しみたい。 |
| 仕事上海外生活をしなければならない。 |
| 映画を字幕に頼らずに楽しみたい。 |
|
目標には、期限の設定が必要です。いつまでにそれを達成したいのか、50年後でいいのか、それとも1年以内なのか、5年先なのか。 |
1年後 |
| 5年後 |
| 10年後 |
| 20年後 |
| 50年後 |
ページトップへ戻る
決まったら、そのために必要な英語の分量を量って、1日に習得しなければならない分量を算出しましょう。
私の経験上、限界は150語/日です。逆にそれ以上の目標は無理だということです。
ただし、その日のうちに覚える必要はありません。
繰返し触れることが肝腎なので、「げっ、1日150語なんて覚えられるわけない」と悲観しないように。
この150語が上手く配分されている素材を入手します。音素材と文字素材です。
毎日の分量は決まってますね。とにかくよく聞いて、同じように言えるように練習してください。
ひたすら音読です。モデルの音素材と同じ様に言う。これがステップ1です。
きっと、ほっぺたが筋肉痛になるでしょう。ならない人は練習が足りません。
筋肉痛を乗り越えたら、第1段階「準備運動」終了です。ようやく英語の学習を始められるようになりました。
検定や資格試験はギャンブルにあらず。
一夜漬けで受かったものはいない。
運試しで受ける人がいます。お金の無駄です。逆に、
ダメだと思って受けたら、なぜか高得点だったり、受かってしまったりすることもあるのです。
人間の脳みそをあなどってはいけません。どこかにしまい込んであるのをあなたが忘れているだけなのです。
普段の不断の成果の証明である。
素直に吸収した者ほどステップアップも早い。
第10条のトップへ戻る
ページトップへ戻る
|